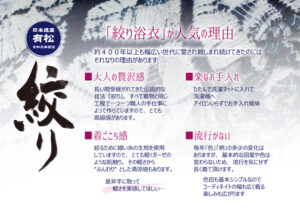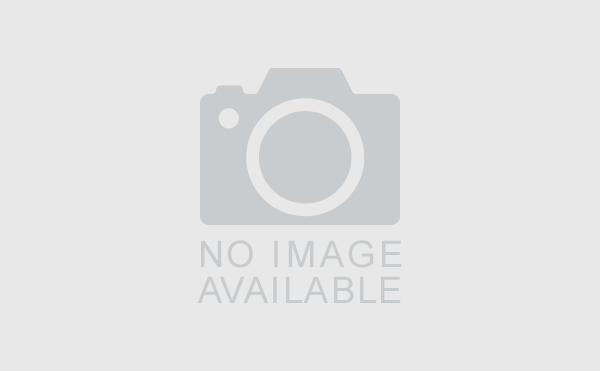山葡萄について
山葡萄製品の色や艶の変化について
山葡萄製品は、使い込むことで色や艶が変化します。
初めは色が明るく、時間が経つにつれて飴色に変わり、艶が出てきます。
しかし、ただ眺めているだけでは色の変化を楽しむことはできません。
皮脂が重要な役割を果たしており、人の手で触れることで色が変化します。
そのため、シュロたわしや豚毛のブラシなどでお手入れすることが大切です。
1. 山葡萄とは?
山葡萄(やまぶどう)は、標高の高い山地に自生するブドウ科の蔓性落葉木です。
日本では主に東北地方に多く見られ、昔から実はジュースやワインに利用されてきました。また、蔓は丈夫なため、谷間などに架けられる橋の材料や、籠や生活道具としても使われていました。
一般的にスーパーなどでよく見かけるブドウとの違いは、実の大きさです。山葡萄の実は小さく、ブルーベリーほどの大きさになります。
味は酸味が強く、糖度が低いため、加工せずそのまま食べる人は少ないでしょう。
2. 山葡萄の蔓の種類
山葡萄の蔓は、大きく分けて2種類あります。
- 山皮(やまがわ)
山の中腹の水辺から離れた場所に自生するものです。
蔓の表面に赤茶色の膜があり、「赤皮」とも呼ばれています。 - 沢皮(さわがわ)
沢沿いや水辺付近に多く見られるものです。
蔓の表面の膜は、山皮に比べて白っぽい茶色をしており、「白皮」とも呼ばれています。
蔓の採れる量について
沢皮は、蔓の採取量が全体の3割しかないため、希少な材料です。
また、山葡萄は人里離れた奥山に自生しており、採取するためには長い時間がかかります。
そのため、採取中には熊の出没に注意する必要があります。
熊は山葡萄の実を好んで食べますし、他の動物にも警戒が必要です。
籠や小物を作るための材料について
山葡萄には、主に4種類の蔓が使われます。
- 山皮
- 沢皮
- 山皮の削皮
- 沢皮の削皮
「削皮」とは、蔓の表面の膜を削り取ったものを指し、これを「二番皮」とも呼びます。
山皮と沢皮の削皮の特徴
- 山皮の削皮
表面の赤い膜を削ると、黄色っぽい茶色になります。
籠や小物の素材として最もよく使われており、当店の小物もこちらの皮をメインで使用しています。 - 沢皮の削皮
表面を削ると白っぽい茶色になり、希少性が高いです。
そのため、主に高級な籠に使われることが多いです。
膜ありと削皮の違い
- 膜あり
表面の膜が皮脂を吸収しやすいため、色の変化が早く現れます。
ただし、特に山皮の膜は剥がれやすく、剥がれた部分が汚く見えることがあります。
使い込むことで変色し、目立たなくなりますが、購入時に汚く見える場合があります。 - 削皮
表面の膜を削ったものは、見た目がきれいで、なめらかな表面になります。
艶が出るのは早いですが、色の変化は膜ありに比べて遅くなります。
それでも、十分に色の変化を楽しむことができます。
3. 伐採から材料に加工するまでの工程
かごに加工できる山葡萄の蔓には、
「削皮(さくひ)」「沢皮(さわがわ)」「山皮(やまがわ)」などの種類があります。
まず、それらの蔓を採取し、表面に残っている古い皮(鬼皮)を剥ぎ取ります。
すると、中から新しい皮が現れます。
籠に使用するのは、この新しい皮の部分です。
次に、この皮を蔓から丁寧に剥ぎ取ります。
使える部分、使えない部分、節があるもの、曲がったものなど、一本一本状態が異なります。
すべての素材を無駄にしないように、それぞれの特徴に合わせて加工していきます。
サイズ別の加工について
山葡萄の蔓は、用途に応じて
3mm、6mm、8mm などの幅に手作業で切り分けられます。
この切り分けからなめし(柔らかくする)加工まですべて手作業です。
特に3mmヒゴは繊細な作業で、
1つの籠の材料を作るのに5〜10日間ほどの時間がかかります。
この3mm幅の籠は、熟練の職人でなければ正確に編み上げることができない高度な技術が必要です。
素材ごとの加工ポイント
- 沢皮・山皮は、表面の皮が剥がれないように細心の注意を払って加工します。
- 削皮(さくひ)は、さらに表面に自然なふくらみを持たせるように削り取ります。
この作業により、削皮特有の美しい光沢が生まれます。
4. 材料から籠や小物になるまでの工程
籠や小物を作るには、すべて「型(かた)」が必要です。
まず最初に、そのアイテムの形を決めるために「型」を作り、
サンプルを制作しながら、何度も修正を繰り返して形を整えていきます。
この型作りこそが、作品の善し悪しを左右する最も重要な工程です。
ヒゴの使い分け
前の工程(3)で作られたヒゴを使用しますが、
籠の部位やデザインによってヒゴの厚みを調節します。
この作業もすべて、1本1本手作業で行います。
ヒゴは柔らかくするために濡らしながら編み込んでいきます。
完成後は陰干しでゆっくりと乾燥させ、形をしっかりと固定させます。
仕上げの細かい作業
乾燥後は、ヒゴの表面に残っている細かな**ケバ(毛羽立ち)**を
一つ一つハサミで丁寧にカットして整えていきます。
その後、仕上げとして表面に**うっすらと蜜蝋(みつろう)**を塗ります。
この工程では、豚毛のブラシを使って丁寧に塗り込んでいきます。
蜜蝋の役割と経年変化
蜜蝋は、最初のうちはヒゴの表面を保護する役割があります。
使い込むことで、蜜蝋は手の油(皮脂)と一緒にヒゴに染み込み、
ヒゴ自体が美しい光沢を放つようになっていきます。
また、柔軟性も増し、より丈夫で長く使える素材へと育っていきます。
5. 編み方の種類
山葡萄の籠や小物には、
数十種類もの編み方があります。
大きく分けると、
- 平面的な編み方
- 立体的な編み方
の2種類に分けられます。
平面的な編み方
代表的なのが「網代編(あじろあみ)」です。
この網代編を基本に、
- 枡網代(ますあじろ)
- 連続枡網代
など、さまざまなバリエーションがあります。
平面に美しい模様をつくりながら編むこの方法は、
シンプルながらも繊細な仕上がりが魅力です。
立体的な編み方
「六角編(ろっかくあみ)」
この編み方は、六角形のパーツを一つひとつ編み込んでから、
さらにそれらを繋ぎ合わせて一つの籠に仕上げていく技法です。
網代編に比べて、2.5〜3倍のヒゴを使用するため
重みは出ますが他にはない存在感と風格が感じられます
その他の編み方
他にも、「石畳編(いしだたみあみ)」など
職人の技術とセンスが光る編み方がたくさんあります。
6. 使用上の注意と、日頃のお手入れについて
山葡萄の籠と末永く付き合っていくために大切なのは「愛情」です。
日々のお手入れや保管方法ひとつで、仕上がりや風合いは大きく変わってきます。
山葡萄籠工房では、天然素材が持つ風合いや魅力を最大限に活かすことを大切にしています。
そのため、ご使用の際にいくつか注意していただきたい点があります。
ご使用時の注意点
使いはじめのころは、山葡萄のヒゴが少し硬めの質感のため、
絹やカシミヤなどの繊細な素材の洋服に擦れると、生地が傷む可能性があります。
使い込むうちに、自然と表面がなめらかになり、やさしい肌ざわりに変わっていきます。
それまでは、デリケートな素材の服と一緒に使う際には、十分ご注意ください。
素材の特徴について
天然素材である山葡萄の蔓には、もともと
- ヒゴの節(ふし)
- ムラ(色味や繊維のばらつき)
- 繊維に沿った縦割れ
などが見られますが、強度にはまったく問題ありませんのでご安心ください。
むしろ、使い込むほどにそれらが馴染み、風合いが深まり、
「自分だけの逸品」へと育っていきます。
水分・湿気にご注意ください
山葡萄の籠は天然素材のため、水や湿気をとても嫌います。
水に濡れてしまった場合は、
すぐに乾いた布で水分を拭き取り、形を整えて陰干ししてください。
※注意:
ドライヤーやストーブ、直射日光や車内の高温などでの乾燥は厳禁です。
天然素材が傷んでしまいます。
カビの予防と保管方法
カビは、発生してからでは手遅れになることもあります。
一度根が蔓の内部に入ってしまうと、取り除くのが難しくなります。
以下の条件が揃うと、カビは繁殖しやすくなります。
- 汚れがついたまま
- 高温な環境
- 湿度が高い場所
これを防ぐためにも、風通しの良い、涼しい場所で保管するようにしてください。
楽しみ方のひとつとして…
山葡萄の籠は、インテリアとしてもとても映えるアイテムです。
ドライフラワーを挿して飾ったり、空間を彩るアイテムとして楽しむのもおすすめです。
さいごに
山葡萄の籠や小物は、素材の個性を最大限に活かすため、
すべての工程に時間と手間、そして熟練の技が込められています。
ひと目には見えないところにも、細やかな気配りと職人の想いが宿り、
編み方ひとつで、同じ素材からまったく違う表情が生まれます。
自然素材ならではの温もりと美しさは、
手をかければかけるほど、やさしく応えてくれます。
どうか、お気に入りのひと品として、
長く、大切にお使いいただければ幸いです。